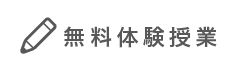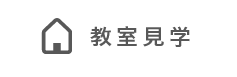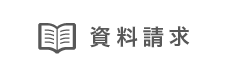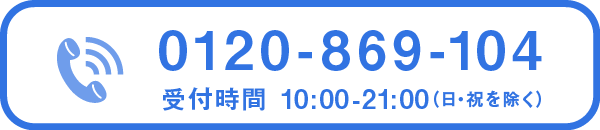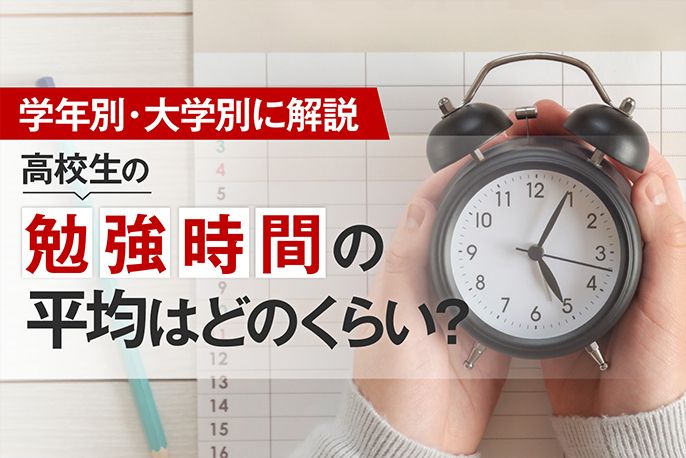この記事の目次
高校生の勉強スケジュール完全ガイド!時間を最大限に活用する方法
更新日:2025/04/15 公開日:2025/04/15
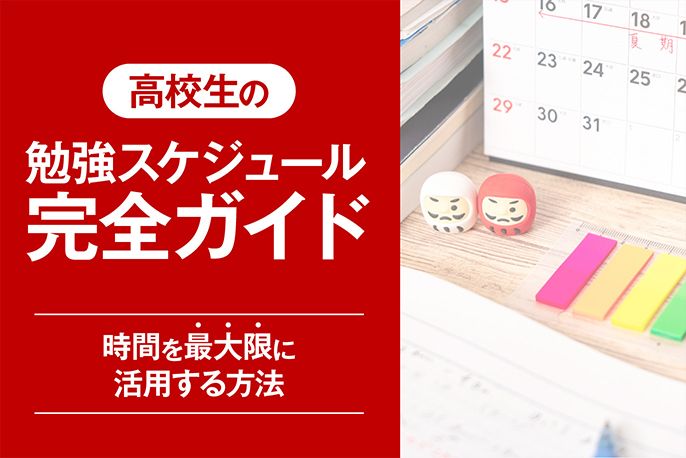
高校生が限られた時間を有効活用し、効率よく学習を進めるためには、適切なスケジュールによる時間の管理が欠かせません。しかし、どのように計画を立てればよいのか悩む人も多いのではないでしょうか。本記事では、高校生が勉強スケジュールを立てるべき理由や、目標達成に向けた効果的なスケジュールの立て方を解説します。日々の学習を無理なく続けるコツや、勉強時間を確保する工夫も紹介するので、自分にあったスケジュールづくりの参考にしてください。
1.高校生が勉強スケジュールを立てるべき理由は?
まずは、高校生がスケジュールを立てて勉強を進めるべき理由を解説します。

1-1.勉強に割ける時間は限られているから
高校生活は勉強だけでなく、部活や学校行事、友人との時間など、さまざまな活動に追われ多忙です。そのため、勉強に使える時間は限られています。限られた貴重な勉強時間を有効活用するためには、優先順位をつけて計画を進めることが不可欠です。スケジュールをきちんと作成すると、無駄な時間が減り、効率的な学習が可能になります。科目や単元の重要度に応じて時間を配分すれば、目標に向かって着実に進んでいけるでしょう。
1-2.計画的に進めるとメンタルが安定するから
計画的に勉強を進めることは、精神的な安定をもたらす効果もあります。スケジュールを立てておくと、「次に何をすればよいか」が明確になり、不安を軽減できるためです。目標を達成していく過程が、モチベーション維持にもつながります。
また、無理のない計画を立てると学習が習慣化し、途中で挫折するリスクを減らせるのもポイントです。計画通りに進めることで達成感や安心感が得られ、それが心の安定にもつながります。
2.高校生に必要な勉強時間の目安は?
高校生が受験に向けて勉強するには、どのくらいの時間を確保する必要があるのでしょうか?目安となる時間を押さえておきましょう。

2-1.受験勉強に必要な総勉強時間
大学受験に必要な勉強時間は、2000〜3000時間程度が目安とされています。高1から勉強を始めるのなら1日2〜3時間程度で十分ですが、高3になってから始める場合は1日10時間以上必要になってしまいます。高3になってから「時間が足りない!」と慌てないためにも、高1から計画的に取り組むことが重要です。
2-2.国公立大学・私立大学で必要な勉強時間
志望するのが国公立大学なのか、私立大学なのかによっても、必要な勉強時間は異なります。
2-2-1.国公立大学合格に必要な勉強時間
国公立大学を志望する場合、勉強時間は3000時間以上を確保するのが一般的です。比較的長い時間が必要になるのは、大学入学共通テスト(旧センター試験)で多科目をカバーしなければならず、時間がかかる傾向があるためです。しっかりとスケジュールを立て効率的に勉強を進めないと、試験本番に間に合わない可能性もあるので、高1から計画的に取り組みましょう。
2-2-2.私立大学合格に必要な勉強時間
私立大学志望の場合、必要な勉強時間は2000〜2500時間程度です。私立大学は受験科目数は少ないものの、各科目で深い理解が求められるため、しっかりと勉強時間を確保する必要があります。高3の夏休みまでに基礎固めを終わらせて、秋以降には志望校の過去問に取りかかるスケジュールで進めましょう。
2-3.難関大学を目指す場合の勉強時間の目安
東京大学・京都大学・早稲田大学・慶応大学などの難関大学を目指すケースの勉強時間は、3500〜4000時間が必要です。高1・高2で基礎固めをし、高3では過去問の演習や応用力の習得に多くの時間を割くことが求められます。難関大学を目指す場合は、高1から受験勉強をスタートさせるのはもちろん、早め早めに進めるスケジュールを立て、計画的に学んでいくことが重要です。
3.高校生の勉強スケジュールの立て方
ここでは、自分に合った勉強スケジュールを立てる方法を、5つのステップに分けて解説します。

3-1.ステップ1:自分にあうツールを選ぶ
勉強スケジュールを毎日適切に管理するためには、自分にとって使いやすいツール選びが大切です。紙の手帳やカレンダー、スマホアプリなど、ツールの種類は多岐にわたりますが、自分が使いやすく、長期的に続けられるものを選びましょう。過去の振り返りや予定の見直しが簡単にできるツールなら、スケジュール管理が楽になります。自分が使い勝手が良いと感じ、見るとモチベーションが上がるものがおすすめです。
3-2.ステップ2:目標実現に必要な勉強総量を把握する
これからの勉強スケジュールを考えるときには、長期目標(例:志望校合格)を明確にし、その目標を達成するために必要な学習内容をリストアップすることが第一歩です。リストアップできたら、各科目や単元ごとに必要な勉強量を具体的に把握し、どの程度の学習時間が必要かを逆算して計画に組み込みます。これにより、目標達成に向けて何をすべきかが明確になり、計画を進めやすくなります。
3-3.ステップ3:科目ごとの優先順位を設定する
勉強の効率を上げるためには、科目ごとの優先順位をつけることが非常に重要です。特に苦手科目や入試で配点が高い科目については、より多くの時間を割り当てるなど、少しでも得点を伸ばすために優先的に取り組みましょう。
3-4.ステップ4:中期・短期目標に分割する
長期目標を達成するためには、まずは1か月〜3か月単位の中期目標を立て、それをさらに1週間の短期目標に分けて設定するのが有効です。中期目標では、模試や定期テストで良い結果を出すことを目指し、それに向けた学習計画を立てます。一方、短期目標では「1週間でこの単元を終わらせる」など、日々の学習で達成感を得られる具体的なアクションを計画すると、モチベーションを維持できます。
3-5.ステップ5:振り返りと調整を習慣化する
スケジュールは、立てるだけでなく、定期的に振り返りをおこない進捗を確認し、調整を重ねることが重要です。計画通りに進まない場合もあるため、達成度を振り返り、うまくいかなかった部分については改善策を見つけましょう。模試やテストの結果を参考に、必要に応じて次の計画を見直し、より効果的な学習方法に変更していきます。この振り返りと調整を習慣化することで、常に最適な学習スケジュールを維持できます。
4.高校生が勉強スケジュールを立てるときのポイント
効率的に勉強を進めるためには、学習の時間をしっかりと計画し、無駄を省くことが大切です。ここでは、高校生が勉強スケジュールを立てる際のポイントを紹介します。
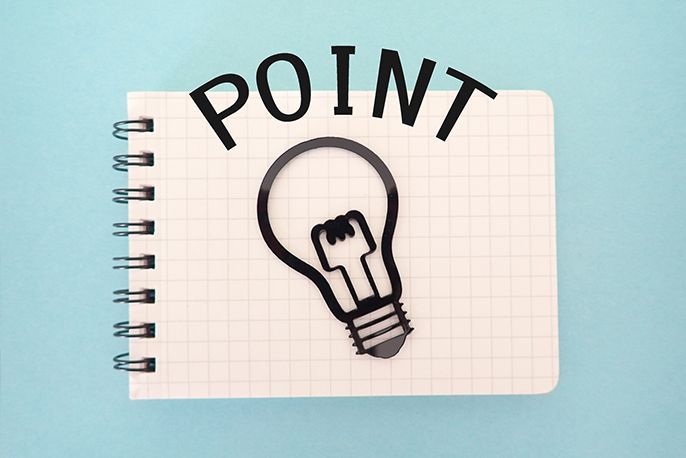
4-1.平日と休日、長期休暇は分けて計画する
高校生は、平日は学校や部活があり勉強時間が限られているため、短時間でも集中して取り組むことが求められます。一方、まとまった時間を確保できる休日は、長時間の勉強を計画するのが効果的です。長期休暇では普段の不足分を補うだけでなく、集中的に弱点を克服する時間としても活用しましょう。各期間にあわせて勉強内容を調整することが、成功への鍵を握ります。
4-2.苦手科目・分野は十分な時間を確保する
受験勉強では、得点が伸びやすい得意科目に偏ってしまう人がいます。しかし、苦手科目や分野にこそ、できるだけ多くの時間を優先的に割くことが大切です。理解が浅い部分を強化するためにも、復習や演習問題に取り組む時間を意識的に確保しましょう。苦手な科目を早期に克服できれば、受験に向けての自信もつきます。
4-3.スケジュールを詰めすぎない
勉強スケジュールを詰め込みすぎると、ストレスや挫折の原因になり、逆効果になってしまうことがあります。空き時間を意識的につくり、余裕を持たせておくと、柔軟に計画を調整できます。スケジュールに余裕があれば、進捗が遅れたときでも焦りやプレッシャーを感じずにすむので、心の負担が軽減されるのもメリットです。
4-4.睡眠時間を削らない
睡眠不足は勉強効率を大きく低下させ、集中力や記憶力にも影響します。特に、成長期の高校生にとっては、8時間以上の睡眠時間を確保するのが望ましいとされています。しっかりと睡眠を取り脳を休息させることは、学習した内容の定着にも必要です。十分な睡眠時間をあらかじめ盛り込んだスケジュールを組んでおけば、「寝た時間だけ勉強が遅れる」と不安になることもないでしょう。
4-5.朝や隙間時間も活用する
夜に連続して3時間勉強するよりも、朝1時間、夜2時間のほうが負担が軽く感じられます。朝は頭がすっきりしており、暗記や集中力が必要な科目に最適な時間帯です。また、通学時間や空き時間などの隙間時間も有効活用できます。単語暗記や短い問題集を進めるなどし、わずかな時間も無駄にせず、効率的に勉強を進めましょう。
5.高校生の勉強スケジュール例
ここでは、高校生の勉強スケジュールの具体例を、平日と休日に分けて紹介します。
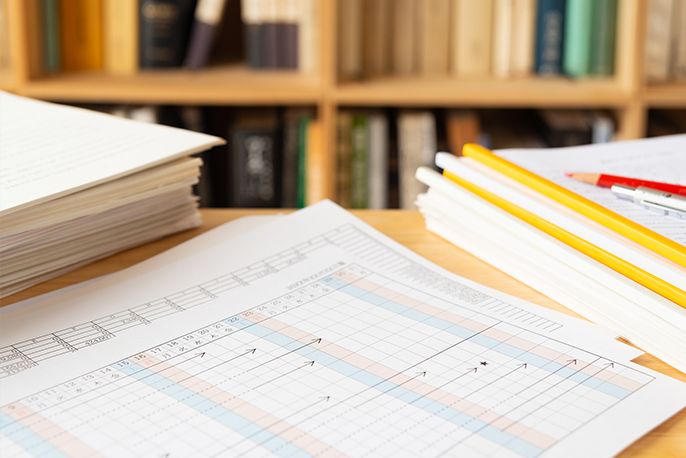
5-1.平日のスケジュール例(高校3年生):合計3時間30分
| 時間帯 | 活動時間 |
|---|---|
| 朝(登校前) | |
| 6:00~7:00 | 復習や暗記 |
| 7:00~7:30 | 学校の準備と朝食 |
| 放課後・帰宅後 | |
| 17:00〜18:00 | 部活・習い事 |
| 18:30〜19:00 | 夕食 |
| 19:00~19:30 | 学校の宿題や予習 |
| 19:30~20:30 | 重点科目の勉強(苦手科目を優先) |
| 20:30~21:00 | 休憩 |
| 21:00~22:00 | 定着を意識した復習と次の日の準備 |
| 22:00〜23:00 | 入浴・就寝 |
平日は学校や部活で忙しいため、効率よく勉強時間を確保することが大切です。朝の時間を有効に使って復習や暗記をおこない、放課後は学校の宿題や予習をこなした後、重点的に苦手科目を勉強しましょう。夜は復習に重点を置き、次の日の準備をしてから寝ることで、翌日の勉強にスムーズに入れるようになります。
5-2.休日のスケジュール例(高校3年生):合計9時間30分
| 時間帯 | 活動時間 |
|---|---|
| 午前中 | |
| 8:00~9:30 | 重点科目の演習(問題集や過去問) |
| 9:30~10:00 | 休憩(軽食やリラックス) |
| 10:00~12:00 | 苦手科目の克服や基礎固め |
| 午後 | |
| 13:00~14:00 | 比較的得意な科目の復習 |
| 14:00~15:30 | 模試の解き直しや過去問分析 |
| 15:30~16:00 | 休憩 |
| 16:00~17:00 | 暗記や短時間でできる学習(単語帳や要点チェック) |
| 夜 | |
| 19:00~20:30 | まとめの勉強(その日学習した内容の振り返り) |
| 20:30~21:00 | 休憩 |
| 21:00~22:00 | 軽い復習や次の日の準備 |
| 22:00〜23:00 | 入浴・就寝 |
休日は、午前と午後に重点的な勉強を集中して行い、夜の負担を軽くすることが効果的です。朝から昼にかけて、重点科目や苦手科目にしっかり時間をかけ、午後には比較的得意な科目や過去問の解き直しを行い、学習内容を定着させます。夜は振り返りや軽い復習を中心に進め、次の日の準備をして早めに寝ることで、次の日の勉強をスムーズに始められるようになります。
このように、夜の負担を減らすようにすると、心身のリフレッシュも確保でき、勉強効率が高まります。
6.高校生が勉強の効率を上げるコツ
勉強の効率を上げるためには、適切な環境づくりや集中力を維持する工夫が必要です。ここでは、勉強効率を上げるためのポイントを紹介します。

6-1.勉強環境を整える
勉強する場所を整えると、集中力を維持しやすくなります。デスク周りは必要最低限のものだけを置き、スマホやゲームなど集中を妨げるアイテムは、別の部屋に置くなど物理的に遠ざけましょう。また、自然光が入る明るい場所や、暗すぎず適切な照明のある場所を選ぶことも大切です。環境が整うと、気を散らすものが減り、学習に集中できるようになります。
6-2.集中力を高めるルーティーンを見つける
勉強を習慣化するためには、勉強を始める時間を毎日固定し、習慣化するのが有効です。同じ音楽を流したり、特定の飲み物を用意したりするなど、勉強を始める「スイッチ」をつくることがポイントです。ほかにも、勉強前に軽いストレッチや深呼吸をおこなうと、身体と心がリセットされ、集中モードに切り替えやすくなります。
6-3.タスクリストを活用する
1日の目標を明確にするために、学習タスクをリスト化することも大切です。タスクを細分化して、一つずつ達成すると達成感が得られ、モチベーションを維持できます。優先順位をつけ、重要なタスクを先にこなすと、効率的に勉強を進められるのもメリットです。やるべきことを漏らさずこなすためにも、タスクリストをつくり勉強の進捗を視覚的に確認しましょう。
6-4.適切に休憩をとる
長時間勉強を続けると集中力が低下するので、適切なタイミングで休憩を取ることも大切です。休憩中は目を閉じたり軽い運動をしたりすると、頭をリフレッシュできます。スマホを見ると、ついLINEの返事をしてしまったり、動画をダラダラ見たりすることで、決めた休憩時間を守れなくなりがちなのでできるだけ避けましょう。
また、勉強が長時間続く場合は、短い仮眠や散歩を取り入れて、気分転換するのも効果的です。集中力を持続させ、勉強効率を向上させるためにも、適切な休憩が必要です。
7.スケジュール管理が難しいなら個別指導塾がおすすめ
勉強スケジュールを立てても、計画通りに進めるのが難しいと感じる人は少なくありません。特に、部活やバイトと勉強を両立しなければならない場合、自分だけで管理するのは大変です。そんなときは、個別指導塾を活用するのも一つの方法です。個別指導塾なら、一人ひとりの志望校や目標に応じた最適な勉強スケジュールを提案してもらえるため、無駄なく学習を進められます。部活やバイトを続けたい場合も、限られた時間を最大限活用するための具体的なアドバイスを受けられます。
さらに、進捗状況や模試の結果をふまえて、スケジュールを随時調整してくれるので、計画倒れを防ぎやすくなるのもメリットです。自分だけではモチベーションを維持しにくいと感じる場合や、自宅ではダラダラしてしまうといった人も、専門家のサポートを受けることで、学習習慣の定着がスムーズになり最後まで計画的に勉強を進められます。

8.まとめ
勉強スケジュールを立てることは、学習効率を上げるだけでなく、精神的な安定にもつながります。平日と休日、長期休暇を区別して計画を立て、無理なく続けられるスケジュールを組みましょう。重要なのは、無理をしすぎず、自分にあった方法で勉強を「続ける」ことです。完璧を目指すのではなく、自分に合ったペースで学習を進め、目標達成に向けて努力を積み重ねましょう。スケジュール管理に自信がない場合や、一人で勉強を進めるのが難しいと感じるなら、個別指導塾がおすすめです。プロの指導を受けることで、効率的に学習を進められるようになり、モチベーションの維持にも役立ちます。
個別指導塾スクールIEでは、一人ひとりの状況に合わせ、学ぶ教科や回数、時間帯を自由に選べる柔軟な学習スタイルを提供しています。「志望校合格に向けた対策を強化したい」「苦手な科目を重点的に克服したい」「習い事や部活、バイトと両立したい」など、それぞれの目標やニーズに合わせた指導が可能です。まずは気軽にご相談ください。

学年別の個別指導コース
執筆者:スクールIE コラム編集部
お子さまの個性に合わせた
学習方法見つけませんか?
教育のプロフェッショナルが
保護者様の様々なお悩みに答えます!
体験授業で3つの無料体験

高校生は塾にいつから通うべき?おすすめ開始時期と塾選びのポイントを解説
高校生の勉強時間の平均はどのくらい?学年別・大学別に解説【大学受験】






 受付 10:00~21:00(日祝を除く)
受付 10:00~21:00(日祝を除く)