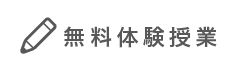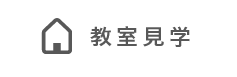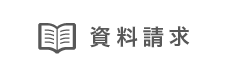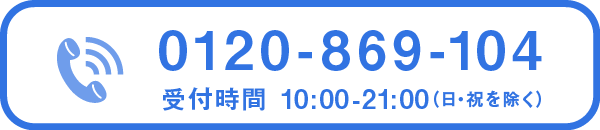この記事の目次
学校推薦型選抜とは?仕組みや一般選抜・総合型選抜との違いを徹底解説!
更新日:2025/04/15 公開日:2025/04/15

学校推薦型選抜は、高校での成績や活動実績を評価する入試方式で、一般入試とは異なる対策が早い段階から必要です。本記事では、学校推薦型選抜の仕組みや種類、対策法を詳しく解説。成功のカギとなる自己分析や志望校リサーチのポイント、効果的な学習法も紹介します。個別指導塾を活用した対策法も解説するので、確実に合格を勝ち取りたい方はぜひ参考にしてください。
1.学校推薦型選抜とは?
学校推薦型選抜は、高校での成績や活動実績を評価する入試方式の一つです。まずは、その特徴や近年の動向について解説します。

1-1.一般選抜と並ぶ大学入試の主要方式
学校推薦型選抜は、一般選抜と並ぶ大学入試の主要な方式の一つで、出願するためには高校の推薦が必須となります。高校からの推薦を得るためには、調査書の学習成績(評定平均値)の基準をクリアする必要があり、一部の大学では浪人制限が設けられています。一般選抜が筆記試験の得点を重視するのに対し、学校推薦型選抜では書類審査、面接、小論文など、多面的な評価方法が採用されます。これにより、学力試験では測れない、人物像や適性を評価できるのが特徴です。
1-2.学校推薦型選抜が拡大している背景
近年、学校推薦型選抜による入学者数の割合が増加傾向にあります。特に私立大学では、令和5年度に全入学者の約41%が学校推薦型選抜で入学しています。
| 国公立大学 | 私立大学 | |
|---|---|---|
| 入学者数 | 132,909人 | 491,706人 |
| 学校推薦選抜での入学者数(割合) | 21,098人 (約15.8%) |
203,375人 (約41%) |
※文部科学省「令和5年度国公私立大学入学者選抜実施状況」を参考に編集部にて作成
この拡大の背景には、少子化にともなう受験生獲得競争の激化があります。特に私立大学では、早期に優秀な学生を確保するため、学校推薦型選抜の枠を拡大する動きがみられます。また、医学系の地域枠や理系女子枠の導入など、特定分野の人材確保を目的とした特別枠の設置も増えてきました。これにより、学力試験では測れない表現力や課外活動の実績を評価しやすくなり、多様な学生を受け入れる仕組みが整いつつあります。
2.学校推薦型選抜の種類と特徴
学校推薦型選抜には、主に「指定校制推薦」と「公募制推薦」、「地域枠推薦」の3種類があります。それぞれの特徴や選考基準について理解し、自分にあった方式を選ぶことが重要です。

2-1.指定校制推薦とは?
指定校制推薦は、大学が特定の高校を指定し、その高校内で推薦枠を設ける方式です。出願資格を得るには、指定された高校の校長推薦が必要になります。この制度は、大学と高校の信頼関係に基づいており、合格率が比較的高い点が特徴です。ただし、高い評定平均や人物評価が求められるため、大学進学後の学業成績や生活態度も重視される傾向があります。
2-1-1.どんな人に向いている?
指定校推薦は、以下のような人に向いています。
・高校の成績が安定している人(特に評定平均が高い人)
・志望校・学部が決まっており、推薦枠がある高校に通っている人
・大学側が求める人物像に合致し、校内選考を通過できる人(生活態度や課外活動も評価されるため)
2-2.公募制推薦とは?
公募制推薦には「一般推薦」と「特別推薦」の2種類があり、どの高校からでも条件を満たせば出願できます。
| 公募推薦の方法 | 内容 |
|---|---|
| 一般推薦 | 学習成績(評定平均)を基準に選考される。校長推薦が必要だが、どの高校からでも出願可能 |
| 特別推薦 | スポーツや文化活動の実績、資格・検定の取得を基に選考される |
公募制推薦は指定校推薦と比較して、人気のある大学・学部では倍率が高くなる傾向があります。そのため、面接や小論文、学力試験などの十分な対策も必要です。
2-2-1.どんな人に向いている?
公募推薦は、次のような人に適しています。
<一般推薦>
・高校の定期テストで高得点を安定して取れる人
・一般選抜と並行して対策を進めたい人
・面接や小論文が得意な人
<特別推薦>
・スポーツや文化活動で全国・地方大会などの実績がある人
・特定の資格(英検・TOEIC・簿記など)を取得している人
2-3.地域枠推薦とは?
地域枠推薦は、特定の地域出身者や、卒業後にその地域での就職・活動を条件とする推薦枠です。主に医学部・教員養成系学部で導入されており、地元の人材確保を目的としています。奨学金や学費免除などの経済的支援が提供される場合が多いですが、その場合、卒業後に地域での一定期間の勤務義務が発生するケースがほとんどです。
2-3-1.どんな人に向いている?
地域枠推薦は、以下のような人に向いています。
・医療・教育・福祉など、地域貢献を重視する分野を志望する人
・卒業後の義務勤務を受け入れられる人
・奨学金や学費免除の支援を受けたい人
3.学校推薦型選抜の出願条件と評価基準
学校推薦型選抜に出願するには、一般選抜とは異なる特有の条件があります。ここでは、出願前に必ず確認すべき条件と評価基準について詳しく解説します。

3-1.出願に必要な条件
学校推薦型選抜に出願するためには、いくつかの基本条件を満たす必要があります。
3-1-1.学校長の推薦が必要
学校推薦型選抜のもっとも基本的な条件は、高校の学校長による推薦を受けることです。この推薦を得るためには、各大学が定める「全体の学習成績の状況(評定平均)」や、学科ごとの成績条件を満たさなければなりません。これらの基準は大学ごとに大きく異なるため、出願前に確認することが重要です。
3-1-2.専願が原則だが併願可の大学もある
学校推薦型選抜は、原則として「専願(合格した場合は必ず入学)」です。ただし、関西地区の私立大学を中心に、他大学との併願を認める学校も増えています。特に指定校推薦の場合、合格後の辞退は原則不可とされ、辞退すると翌年以降、その高校への推薦枠がなくなる可能性があるため、本当に志望する大学かどうかをよく考慮したうえで、慎重に判断することが重要です。
3-2.評定平均(内申点)とは?計算方法と基準
評定平均は、学校推薦型選抜におけるもっとも重要な条件の一つで、高校1年生〜高校3年生の1学期までの全科目の成績(5段階評価)の合計を科目数で割って算出します。さらに、全体の評定平均に基づき、以下のように学習成績概評が示されるのが一般的です。
| 全体の学習成績の状況 | 学習成績概評 |
|---|---|
| 4.5〜5.0 | A |
| 3.5〜4.2 | B |
| 2.7〜3.4 | C |
| 2.6〜1.9 | D |
| 1.8以下 | E |
大学によって、「評定平均4.5以上」「学習成績概評A以上」などの条件が設定されています。また、一部の大学・学部では、特定の教科(例:数学4.3以上、英語4.0以上)に条件を設けている場合もあります。
3-3.その他の評価基準
一部の大学では、学校推薦型選抜であっても、大学入学共通テストの成績や学力試験を出願条件に含める場合もあります。特に国公立大学では、学力試験を重視する傾向があるため、学校推薦型選抜でも学習対策が必要です。一方、学力試験が不要な場合では、小論文や面接での評価が合否を大きく左右する要素となります。活動実績や英検®、簿記、情報処理などの資格が評価対象になることもあるため、早めの対策と準備が必要です。
4.学校推薦型選抜の選考方法と試験内容
学校推薦型選抜の選考は、書類審査・面接・小論文が基本的な評価・選考手段です。文部科学省は、各大学が実施する評価方法(小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績等)、または共通テストのうち、少なくともいずれか一つの活用を必須とする指針を示しています。そのため、これらの活用が増えている傾向にあります。ここでは、「書類審査」「小論文・面接」「学力試験」について、詳しく解説します。

4-1.書類審査(調査書・推薦書)
学校推薦型選抜においては、高校の調査書や推薦書が重要な評価要素となり、受験生の学業成績や人物像を示す資料として扱われます。調査書には、評定平均値だけでなく、部活動・ボランティア活動・取得資格などの情報が記載されます。これにより、受験生の高校生活全般における努力や意欲が評価される仕組みです。推薦書は高校の先生が作成し、大学はこの推薦書をもとに、受験生の適性や求める人物像とのマッチングを判断します。
4-2.小論文・面接など
小論文や面接は、受験生の思考力や表現力・適性を測る重要な選考要素です。小論文では、論理的な構成力や表現力が評価されます。学部ごとに課題の傾向が異なり、社会問題に関する考察を求めるものや、志望分野に関する知識を問うものなど、さまざまな形式が存在します。面接では、学習意欲・志望理由・将来の展望が問われることが多く、プレゼンテーションを課す大学では、志望分野に関する知識や発表力が試されます。これらの試験では、受験生の主体性や表現力が求められるため、普段の生活のなかでも意識する必要があるでしょう。
4-3.学力試験
近年、学校推薦型選抜でも、学力試験を課す大学が増加しています。特に国公立大学では、大学入学共通テストの成績を出願条件とするケースが多くなりました。私立大学では、適性検査や基礎学力試験を導入する傾向にあります。また、一部の大学では、英語外部検定(英検®・TOEICなど)を評価対象とすることで、受験生の英語力を測るケースもあります。学力試験の難易度や出題範囲は大学によって大きく異なるため、志望校の過去問や募集要項をよく確認し、適切な対策を講じることが必要です。
5.学校推薦型選抜と他の入試方式の違い
学校推薦型選抜は、一般選抜や総合型選抜とどのように異なるのでしょうか。ここでは、それぞれの選考基準や受験時期の違いについて解説します。

5-1.一般選抜との違い
まずは、一般選抜とどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
5-1-1.選考基準と評価方法の違い
学校推薦型選抜は、高校での学習成績(評定平均値)、課外活動の実績、取得資格などを評価する入試方式です。大学によっては、特定の資格や活動実績を評価基準に含めることもあります。総合的な人物評価がおこなわれるため、日々の学業成績や活動実績の積み重ねが重要となります。一方、一般選抜は、学力試験の結果が合否を決める主な基準であり、出願時の学習成績の基準は設けられていない大学が多いのが特徴です。受験生の能力を試験当日の成績のみで判断するため、高得点を取ることが求められます。
5-1-2.受験時期と合格率の比較
一般選抜の試験が1月〜3月に実施されるのに対し、学校推薦型選抜は11月〜12月に実施されることが多く、スケジュールにも違いがあります。一般選抜では合格率が低く、特に難関大学では倍率が高くなる傾向があります。一方、学校推薦型選抜では大学ごとに倍率の幅が大きく、特に「指定校推薦」は校内選考をクリアすればほぼ確実に合格できます。しかし、「公募制推薦」は大学・学部によっては一般選抜並みの競争率になることもあるため、対策が必要です。
5-2.総合型選抜(旧AO入試)との違い
総合型選抜(旧AO入試)は、学校推薦型選抜と同様に学力試験以外の要素を重視する入試方式ですが、選考プロセスや評価基準に違いがあります。
5-2-1.選考プロセスの違い
学校推薦型選抜は高校の推薦が必要ですが、総合型選抜は出願者が自己推薦できる方式です。そのため、総合型選抜はより個人の主体性や特性を重視する入試制度といえます。また、学校推薦型選抜は主に評定平均や課外活動の実績が重視されるのに対し、総合型選抜は大学の求める学生像(アドミッション・ポリシー)への適合が評価基準となります。大学によっては、講義の受講や課題提出、複数回の面接などを通じて、長期間の選考がおこなわれるケースもあります。さらに、学校推薦型選抜は面接や小論文が課されることが多いのに対し、総合型選抜ではプレゼンテーションやディスカッションなど、より主体性を重視した試験がおこなわれる傾向があります。そのため、自己表現や論理的思考が求められる点が特徴です。
5-2-2.出願時期の違い
学校推薦型選抜は11月〜12月に出願・試験が集中しますが、総合型選抜は8月〜12月の間で大学ごとに異なるスケジュールで実施されます。また、総合型選抜は選考期間が長く、大学独自の課題提出や実技試験を含む場合があります。そのため、学校推薦型選抜よりも準備に時間をかけることが求められます。なお、学校推薦型選抜と総合型選抜の両方を受験することは原則不可とされているため、どちらを選択するか慎重に判断しましょう。
6.学校推薦型選抜への効果的な対策法
学校推薦型選抜で合格を目指すには、早い段階からの準備が欠かせません。ここでは、高校1年生から意識すべきポイントと、面接・小論文の準備方法について解説します。

6-1.高校1年生から意識すべきポイント
学校推薦型選抜では、高校1年生からの成績の積み重ねが大きく影響します。入試直前に対策しても挽回は難しいため、早期からの計画的な学習が求められます。特に、評定平均(内申点)が重視されるため、1年生の時点から定期テストの成績を意識することが重要です。主要教科はもちろん、保健体育や家庭などの副教科も評価対象になるため、全科目でバランスよく成績を維持するよう努力しましょう。また、部活動やボランティアなどの課外活動も評価対象となることから、積極的に取り組むと有利です。特に、リーダーシップを発揮できる役職や、全国・地方レベルの大会実績があると、評価が高くなる傾向があります。
6-2.面接や小論文の準備の進め方
面接や小論文は、学校推薦型選抜での重要な選考要素です。事前にしっかりと対策をおこない、受験本番に備えることが必要です。面接では「志望理由」「将来の展望」「高校での活動」について具体的に説明できることが求められます。学校でおこなわれる模擬面接を活用し、自分の経験や学びを論理的に説明できるよう練習を重ねましょう。小論文は付け焼き刃の対策が通用しにくいため、高校1年生〜2年生の間に論理的な文章を書く力を養っておくことが大切です。過去問や予想問題を活用し、大学ごとの出題傾向に慣れることが効果的な対策となります。プレゼンテーションが課される場合は、簡潔かつ説得力のある話し方を練習することが重要です。特に、志望分野に関する知識を整理し、分かりやすく伝える力を磨くことで、より良い評価を得られる可能性が高まります。
7.合格を勝ち取るには個別指導塾の活用がおすすめ
学校推薦型選抜の対策は、評定平均の維持や面接・小論文対策など、専門的な指導が求められる場面が多く、個別指導塾の活用が有効です。ここでは、個別指導塾のメリットと、具体的にどのような対策が可能かを解説します。

7-1.学校推薦型選抜の対策が難しい理由
まずは、学校推薦型選抜の対策が難しいのはなぜなのか、その理由を詳しく見てみましょう。
7-1-1.高校ごとの定期テスト対策が必要
学校推薦型選抜では、評定平均の向上が必須となるため、通っている高校の傾向に合わせたテスト対策が必要となります。予備校や集団塾では一律のカリキュラムが多く、高校ごとの定期テストに特化した対策が難しいのが現状です。その点、個別指導塾なら、推薦基準や弱点に合わせた戦略的なカリキュラムを組むことができ、評定アップに特化した学習が可能です。生徒一人ひとりの学力状況に応じた指導が受けられるため、効率的に成績を向上させることができます。
7-1-2.受験対策の情報が少ない
一般選抜と異なり、学校推薦型選抜の具体的な対策情報は限られています。そのため、独学では戦略を立てることが難しく、どのような準備をすればよいのか迷ってしまう受験生も少なくありません。また、大学ごとに選考基準や重視するポイントが異なるため、一般的な対策だけでは対応しきれない場合があります。個別指導塾では、各大学の選考ポイントを把握し、受験生ごとに最適な対策を立てられるため、効率的な学習が可能です。
7-1-3.自己流では面接・小論文対策が難しい
小論文や面接の評価基準は抽象的であり、独学では十分な準備が難しい分野です。特に、小論文では論理的な構成や表現力が求められ、自己流の対策では評価が伸びにくい傾向があります。個別指導塾では、受験生の志望校や志望学部に特化した指導を受けることができ、実践的な対策が可能です。面接練習も繰り返しおこなうことで、自信をもって受験に臨めるようになります。
7-2.個別指導塾でできる対策
続いて、個別指導塾では具体的にどのような対策ができるのかを紹介します。
7-2-1.評定平均を上げるための学習管理
学校推薦型選抜では、評定平均の高さが出願資格や合格に直結します。そのため、定期テスト対策を徹底し、内申点を意識した学習計画を立てることが重要です。個別指導塾では、苦手科目を重点的に指導し、バランスの取れた成績を維持できるようサポートします。また、生徒それぞれの学習ペースにあわせて指導するため、効率的に成績を向上できます。
7-2-2.面接・小論文のマンツーマン指導
面接では、説得力のある受け答えができるように準備することが重要です。個別指導塾では、自信を持って本番に臨めるまで、繰り返し模擬練習をおこないます。小論文指導では、論理的な構成や説得力のある文章を書く練習をおこない、大学の出題傾向に合わせた対策を徹底します。文章構成のポイントや、伝えたい内容を明確にする方法を学ぶことで、より高い評価を得られるようになるのです。
7-2-3.過去の合格実績に基づいた戦略的指導
個別指導塾は、過去の合格者のデータをもとに、大学ごとの傾向に合わせた対策をおこないます。実際の合格者がどのような準備をしたのかを参考にするため、効果的な学習計画を立てられます。このように、無駄のない効率的な対策を進めたいときには、個別指導塾がおすすめです。
8.まとめ
学校推薦型選抜は、高校での成績や活動が評価される入試方式で、早期合格が狙える点が魅力です。ただし、評定平均の維持や面接・小論文の準備が欠かせません。これら独学では難しい部分を補うためには、個別指導塾の活用が有効です。大学ごとの選考基準に合わせた指導を受けることで、より高い合格率を実現できます。
個別指導塾スクールIEでは、生徒一人ひとりの学習状況やライフスタイルに合わせた柔軟な指導をしています。「評定平均を上げたい」「面接や小論文の対策を徹底したい」「志望校に合わせた戦略的な学習を進めたい」など、学校推薦型選抜での合格を目指す受験生に、最適なプランをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

学年別の個別指導コース
執筆者:スクールIE コラム編集部
お子さまの個性に合わせた
学習方法見つけませんか?
教育のプロフェッショナルが
保護者様の様々なお悩みに答えます!
体験授業で3つの無料体験

大学入学共通テストの対策法|基礎知識から各教科のコツまで
自己推薦書の書き方完全ガイド!高校生向けに徹底解説【例文付き】






 受付 10:00~21:00(日祝を除く)
受付 10:00~21:00(日祝を除く)