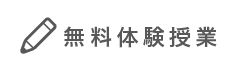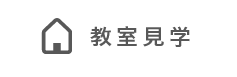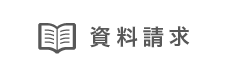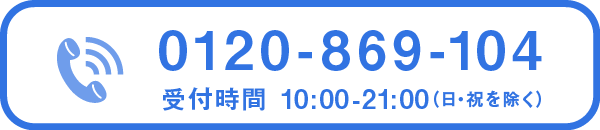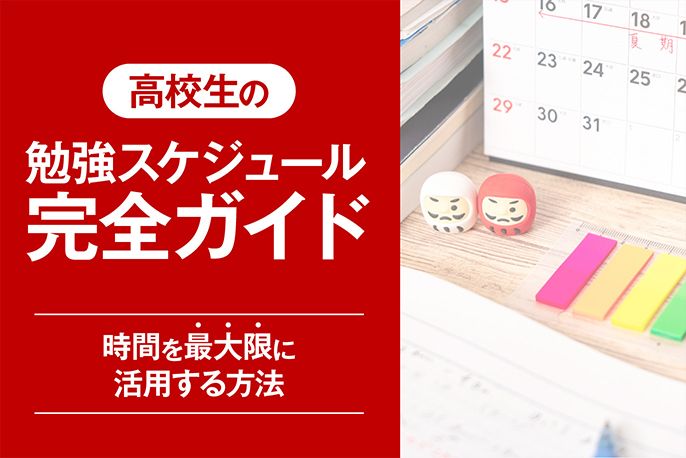この記事の目次
大学入学共通テストの対策法|基礎知識から各教科のコツまで
更新日:2025/04/15 公開日:2025/04/15
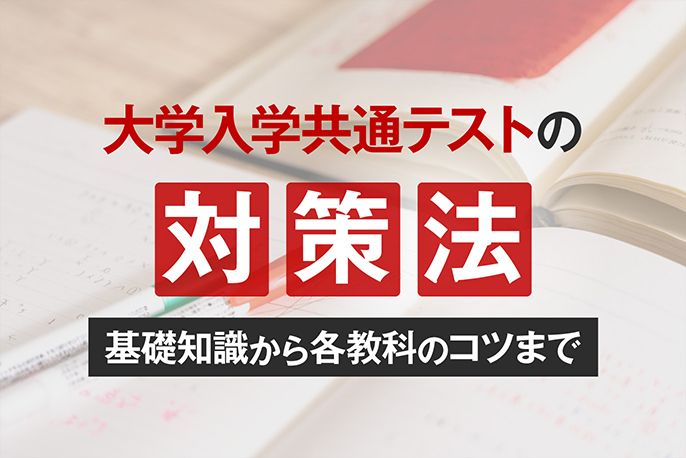
大学入学共通テストは、知識の暗記だけでなく、思考力や判断力も重視される試験です。高得点を取るには、各教科の特性を理解し、計画的かつ戦略的な学習が欠かせません。本記事では、共通テストの基本情報から、効果的な学習計画の立て方、主要教科・科目ごとの具体的な勉強法や得点アップのコツまで詳しく解説します。効率的に対策を進め、目標点数突破を目指しましょう。
1.大学入学共通テストとは?
大学入学共通テストは、2021年に導入された全国規模の大学入試試験です。まずは、共通テストの基本情報やセンター試験との違い、試験のスケジュールについて詳しく解説します。
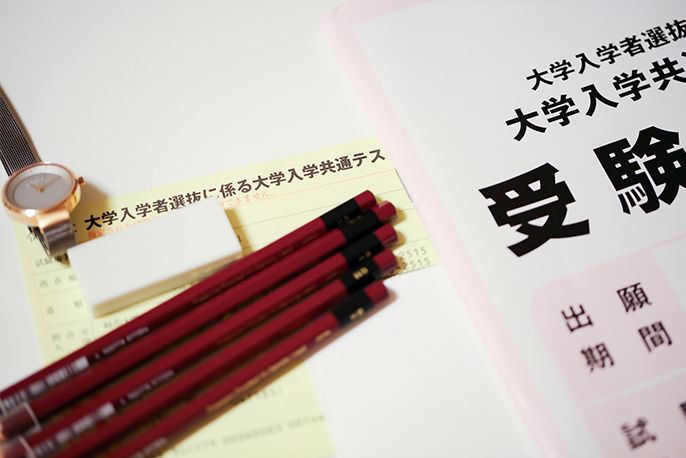
1-1.大学入学共通テストの基本知識
共通テストは、毎年1月中旬に実施され、国公立大学の一般選抜を受験する人や、私立大学の共通テスト利用入試を活用する人などが対象となります。この試験は全問マークシート方式でおこなわれ、記述式問題は含まれていません。受験生は出願大学の入試要件に応じて、必要な科目を選択する必要があり、総合型選抜や学校推薦型選抜でも共通テストを課すケースが増えています。受験資格は、高校卒業見込み者や高卒認定試験合格者など、大学入学資格を持つ人に限られます。出願から成績通知までのスケジュールを把握し、計画的に準備を進める必要があります。
1-2.大学入学共通テストの特徴と旧センター試験との違い
大学入学共通テストは、旧センター試験と比べ、試験内容や出題形式に以下のような違いがあります。
・文章量や資料量の増加:長文問題や資料を読み解く情報処理能力が求められる
・選択肢の文章が長い:ひっかけの工夫が多く、細かいニュアンスの違いを見抜く力が必要
・「思考力・判断力・表現力」を重視:単なる知識問題ではなく、複数の資料を参照しながらの分析・判断が必要
・難問は少ないが、解答時間が短い:出題範囲は教科書の範囲内だが、試験全体のボリュームが多く、時間配分が重要
これらの理由から、大学入学共通テストは「忙しい試験」と言われることが多く、効率的な回答戦略が求められます。
1-3.大学入学共通テストのスケジュール
大学入学共通テストは、以下のスケジュールで進みます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 9月上旬 | 「受験案内」が配布される |
| 9月末〜10月初旬 | 高校を通じて出願する(浪人生などは個別に申し込み) |
| 1月中旬 | 本試験が実施される |
| 追試験 | 本試験の2週間後におこなわれる |
| 4月以降 | 希望者に成績通知が送付される |
大学入学共通テスト後、自己採点をもとに出願先を最終決定します。出願期間は学校により、以下のように異なります。
| 大学の種類 | 出願期間 |
|---|---|
| 私立大学 | 2月上旬〜中期にかけて募集を実施。共通テスト前に出願が締め切られる「事前出願」が多いが、一部では共通テスト後の「事後出願」も可能 |
| 国公立大学 | 大学入学共通テスト受験後の1月下旬~2月初旬の出願が一般的 |
受験スケジュールについては、事前に入試要項をよく確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
1-4.私立大学の一般入試と大学入学共通テスト利用入試の違い
私立大学の多くは、共通テストの成績を活用できる「共通テスト利用入試」を実施しています。一般入試と共通テスト利用入試では試験方式が異なり、求められる得点率も異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。共通テスト利用入試では個別試験が不要な場合があり、共通テストの結果のみで、複数校出願(併願)できるメリットがあります。一方で、共通テスト利用入試は高得点が求められ、一般選抜よりも難易度が高くなるケースがあります。また、国公立大学志望者にとっては、共通テストの得点を活かして私立大学を受験できるため、選択肢を広げられる点も特徴の一つです。そのため、共通テストを活用した受験戦略をしっかり立てることが、合格への鍵となります。
2.大学入学共通テストの学習計画の立て方
続いて、大学入学共通テスト対策を効率的に進めるための、学習計画の立て方を解説します。

2-1.受験科目の選び方
大学入学共通テストは7教科(国語、地理歴史・公民、数学、理科、外国語、情報)21科目で構成されています。
| 教科 | 出題科目 |
|---|---|
| 国語 | 国語 |
| 地理歴史 | 「地理総合、地理探究」「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探」「地理総合/歴史総合/公共」 |
| 公民 | 「公共、倫理」「公共、政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」 |
| 数学 | 「数学I、数学A」「数学I」、「数学II、数学B、数学C」 |
| 理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 |
| 外国語 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 |
| 情報 | 「情報I」 |
出題範囲は主に高校1・2年で学ぶ内容が中心です。受験科目は志望大学の要件を確認し、必須科目と選択科目を決定します。大学によって必要科目が異なるため、志望校の入試要項を早めにチェックすることが重要です。
2-2.目標点数の決め方
国公立大学は共通テストと個別試験(二次試験)の合計得点で合否が決まります。共通テストは「何点を取れば合格」という明確な基準がないため、大学ごとの合格ラインを参考に目標を決めなければなりません。
<一般的な目標の目安>
・7割以上:国公立大学の多くの学部で目指したいライン
・7.5割以上:難関大学を目指す場合に必要なライン
・8.5~9割:東大・京大・医学部など超難関大学を受験する場合
苦手科目での失点を補うため、得意科目は高得点を狙う戦略が有効です。高3の夏までに5〜6割程度を目指し、秋から本格的に得点を伸ばす学習が推奨されます。
2-3.効果的な学習スケジュール
高校1・2年生の学習内容が基礎になるため、実質的には高1から対策が始まっています。高2の3学期(受験のゼロ学期)までに主要科目の基礎を完成させるのが理想です。高3になってからは、以下のスケジュールで進めるとよいでしょう。
| 時期 | 学習内容 |
|---|---|
| 高3の夏まで |
・参考書や教科書レベルの問題を確実に解けるようにする ・典型問題を解く習慣をつける |
| 高3の秋(10月以降) |
・本格的に過去問演習を開始 ・志望校に合わせて目標得点率を意識した学習 ・センター試験の過去問も活用し、基礎力を固める |
| 試験直前1ヶ月 |
・過去問や予想問題集を使った実践演習 ・時間を計って解答する練習 ・本番の試験を想定した時間配分を確認 |
計画的に学習を進めることで、共通テスト本番で最大限の力を発揮できるようになります。
3.大学入学共通テストの勉強法とよくある課題別対策
ここからは、大学入学共通テストの形式に適応するための勉強法や、受験生が直面しやすい課題別の対策について解説します。

3-1.大学入学共通テスト形式に慣れるための勉強法
大学入学共通テストでは、その特徴を理解し、形式に慣れることが得点アップのカギとなります。センター試験の過去問ではなく、大学入学共通テストの過去問題や予想問題を活用し、出題傾向を分析しながらパターン化された解法を習得するとよいでしょう。
効果的な学習ステップは以下のとおりです。
3-1-1.STEP1:基礎力を固める
まずは、教科書の例題や基本問題集を活用し、基礎をしっかり固めましょう。基礎が曖昧なまま応用問題に取り組むのは、効率的ではありません。公式や基本的な解法をしっかり理解し、応用問題に対応できる力を養うことで、試験での安定した得点が可能になります。
3-1-2.STEP2:共通テスト形式の問題を解く
基礎を固めたら、共通テスト形式に沿った問題演習をおこないましょう。時間を測りながら演習し、本番のペースを掴むことが重要です。共通テストは時間との闘いでもあるため、1つの大問に時間をかけすぎないよう意識しましょう。
3-1-3.STEP3:共通テスト模試を受ける
模試を活用し、実際の試験形式に慣れることも大切です。模試は単なる実力チェックとしてだけでなく、時間配分や試験の流れを掴む機会としても活用しましょう。また、共通テストのマークシート形式に慣れ、マークミスを防ぐ練習にもなります。模試後は必ず復習をして間違えた問題を分析し、弱点克服に取り組みましょう。
3-1-4.STEP4:過去問や予想問題で実践演習
試験直前は過去問や予想問題を活用し、本番を意識した演習をおこないます。「本番通りの時間で解く」ことを心がけ、制限時間内に解き終える訓練を繰り返しましょう。過去問演習を通じて、各科目の出題形式や頻出問題を確認し、確実に得点できる分野を強化することが、総合得点の底上げにつながります。
3-2.時間が足りない受験生向けの対策
共通テストは文章量が多く、時間との勝負になる試験です。そのため、効率的に解く力を身に付けることが求められます。ここでは、時間が足りなくなる主な原因別に、対策を解説します。
3-2-1.原因①:読解に時間がかかる
共通テストの問題は文章量が多いため、共通テスト形式の問題集を活用し、速読力を鍛えることが重要です。その際、設問を先に確認し、必要な情報を素早く探し出す練習をすると効果的です。
3-2-2.原因②:計算が遅い(数学)
計算ミスを防ぎ、素早く正確に解答できるようにするには、基礎的な計算力を鍛える必要があります。日常的に計算問題を反復し、計算スピードを向上させましょう。センター試験の過去問を活用し、実践形式で解く練習も必要です。
3-2-3.原因③:問題の解き方が分からない
問題の解法が思い付かないなど、問題の解き方が分からないときには、基本的な問題集で基礎を徹底的に固めることが重要です。典型問題を集中的に解くことで、素早く解法を思い出せるようになります。解き方のパターンが身に付くと、初見の問題にも対応できるようになり、解答スピードも上がります。
3-2-4.原因④:実践不足
本番を想定した演習不足も時間が足りなくなる原因です。模試を積極的に活用し、本番の試験環境下で解答する練習をしておくと、緊張感や制限時間に慣れ、実際の試験でも落ち着いて取り組めるようになります。
3-3.ケアレスミスが多いときの対策
時間との戦いになる共通テストでは、時間に追われて焦ることでケアレスミスをしやすくなります。ミスを減らすには、問題を解くスピードを上げ、見直しの時間を確保することがもっとも重要です。特に、問題文の読み飛ばしを防ぐため、設問の条件をしっかり確認し、重要な部分にマーカーを引く習慣をつけましょう。数学の計算ミスを防ぐためには、計算スペースを確保し、整理して書くことがポイントです。解き終わったあとは検算し、ミスがないかを必ず確認するクセを普段からつけることが、得点力向上につながります。
4.大学入学共通テストの主な教科・科目別勉強法と対策
大学入学共通テストに向けて効率的に学習を進めるためには、各科目ごとの対策が不可欠です。ここでは、主な教科・科目別の対策を紹介します。
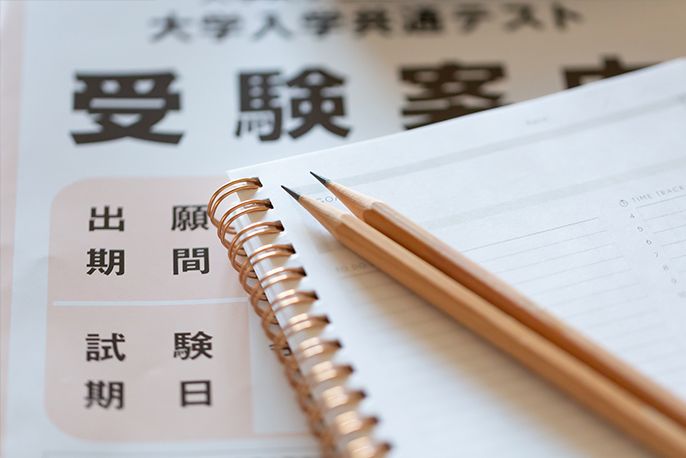
4-1.英語
まずは、英語の対策を、リーディングとリスニングに分けて紹介します。
4-1-1.リーディングの勉強法
共通テストのリーディングは長文読解のみの構成で、発音・アクセントや文法問題は出題されません。また、図表や複数の文章を関連付けて解く問題が出題されるため、速読力と情報整理力が求められます。
<対策>
・速読力を鍛える:日常的に長文を読み、英文の構造に慣れることが重要です。
・設問の先読みをする:設問を先に読むことで、どの部分に注目すればよいか把握できるようになります。
・多様なテーマの英文に触れる:過去問や模試の問題を解いて形式に慣れると、出題傾向を把握できます。
4-1-2.リスニングの勉強法
リスニングのスクリプトは長く、日常会話だけでなく学術的な内容も出題されます。音声が一度しか流れない問題もあり、瞬時に判断する力が必要です。発話者の意図や話者の関係性を問う設問が増加しているため、意識しながら聞く訓練をおこないましょう。
<対策>
・毎日英語を聞く習慣をつける:シャドーイングで発音・リズムを強化し、英語の音になれることが重要です。
・メモを取る練習をする:要点を素早く整理するスキルを身につけることで、リスニング中の情報整理がスムーズになります。
・実際の試験と同じ環境で演習する:本番を想定してヘッドフォンを使うと、試験環境に慣れることができます。
4-2.数学
続いて、数学の対策を解説します。
4-2-1.数学Ⅰ・Aの対策
数学Ⅰ・Aでは、確率や整数の性質など、基礎的な知識を応用する問題が多く出題されます。論理的思考を問う問題も増えており、試行錯誤が必要です。文章量が多いため、読解力も求められます。
<対策>
・基本的な計算ミスを減らす:繰り返し基礎問題を解き、検算するクセをつけましょう。
・時間配分を意識する:制限時間内に解き終わる練習をすると、本番での時間管理の失敗を防げます。
・過去問を利用しながらパターンを掴む:共通テスト形式の問題演習を増やすことで、出題傾向を把握できます。
4-2-2.数学Ⅱ・Bの対策
数学Ⅱ・Bは、グラフや資料をもとに考察する問題が多く、数列の理解が不可欠です。計算ミスを防ぐため、問題演習を通じて計算力を高めることも大切です。
<対策>
・基本的な公式の証明を理解する:公式の成り立ちを説明できるようにすると、応用力が身につきます。
・長文問題に慣れる:計算ミスを防ぎつつ、誘導に従って解答する力をつけるために、長文問題を繰り返し解きましょう。
・計算スピードを上げる:手を動かして解く練習を、地道に繰り返しましょう。
4-2-3.数C
数学Cではベクトルや複素数平面の問題が出題されるため、公式を理解し、適切に活用する練習が必要です。基本問題から応用問題まで幅広く演習することが得点につながります。
<対策>
・複数の解法でアプローチする:同じ問題に対して異なる解き方を学び、柔軟な思考力を身につけましょう。
・例題を反復演習する:代表的な問題パターンを繰り返し解いて、完全理解を目指すことが重要です。
4-3.国語
国語は、現代文と古文・漢文に分けて対策します。
4-3-1.現代文の対策
共通テストの現代文は、複数の文章や資料を比較して解答する問題が増えています。論理的思考力を鍛え、選択肢の根拠を明確にする練習が重要です。
<対策>
・文章の構造を意識して読む:論理展開を把握しながら速読する訓練をおこないます。
・選択肢の根拠を確認する:曖昧な解答を避けるには、明確な論拠を探し出す習慣をつけます。
・漢字や語彙を強化する:語彙力が得点力に直結するため、日常的に語彙を増やす努力をしましょう。
4-3-2.古文・漢文の対策
古文では敬語や和歌の解釈、漢文は句法や書き下し文の理解が必要です。現代語訳との関連を問う問題も出題されます。背景知識を持つことで、文章の意味を深く理解できるようになります。
<対策>
・古文単語・漢文句法を覚える:基本的な重要語句を徹底的に暗記し、読解の精度を高めます。
・音読を取り入れる:声に出して読むことで文章のリズムを掴みやすくなり、内容理解が深まります。
・文章の背景知識をつける:作品のテーマや時代背景を意識すると、作品の文脈をより深く理解できるようになります。
4-4.社会
続いて、社会の対策を解説します。
4-4-1.地理総合・地理探究の対策
地理では、統計資料やグラフの読み取りが重視されます。地域間の比較や空間的な分析を意識し、複数の情報を比較・整理しながら解答する訓練を繰り返しましょう。
<対策>
・統計データの読解練習:人口統計、産業構造、貿易データなどの統計資料から傾向を読み取る練習をしましょう。
・時事問題への意識:ニュースや新聞で取り上げられる地理的な話題にアンテナを張り、地理的視点で考察する習慣をつけましょう。
4-4-2.歴史総合・日本史探求の対策
歴史では、史資料の読解力が問われ、因果関係を正しく理解することが求められます。また、複数の資料を比較しながら考察する問題も増えています。時代背景や出来事の流れを把握することが重要です。
<対策>
・年表を活用した流れの把握:重要なできごとの前後関係や因果関係は年表で把握し、歴史の流れを掴みましょう。
・文化史、社会史への注目:政治史だけでなく、文化や生活の変化にも注目すると、時代の特色を多角的に理解できます。
4-4-3.歴史総合、世界史探求の対策
世界史では、テーマ史や地域横断的な視点を強化することが重要です。史資料から情報を読み取る力をつけましょう。
<対策>
・文明・地域別の特徴整理:各文明や地域の特色を比較表で整理すると、共通点と相違点を把握できます。
・現代との接続:現代の国際問題の歴史的背景を理解し、歴史の連続性を意識しましょう。
4-4-4.公共、政治・経済の対策
公共、政治・経済では、思想家の考え方を整理し、現代の社会問題と結びつけることがポイントです。ニュースや統計データを活用し、背景知識を深めましょう。
<対策>
・グラフ・統計の分析練習:経済指標のグラフや世論調査の結果など、数値データを読み解く力を養いましょう。
・主要な思想・理論の整理:リベラリズム、コミュニタリアニズム、功利主義など、基本的な考え方を整理し、社会問題への適用を考えると効果的です。
4-5.理科
ここでは、理科の対策を解説します。
4-5-1.物理の対策
物理では、公式の意味を理解し、暗記だけでなく導出過程も押さえることが重要です。実験データの読み取りを練習し、 グラフの変化や数値を分析する力をつけましょう。
<対策>
・グラフの作成・分析:実験データからグラフを作成し、傾向を読み取る練習をすることで、データ分析力が向上します。
・計算トレーニング:物理量の単位や次元に注意を払いながら、基本的な計算問題を繰り返し解きましょう。
4-5-2.化学の対策
化学では、日常生活や社会との関連を考慮した問題が増加しています。単なる暗記に頼らず、実験の背景を考えながら学習することが求められます。モル計算や酸化還元反応を確実に解くための演習も欠かせません。
<対策>
・実験手順の理解:実験の各段階の目的や原理を理解することで、実験に関する問題も解きやすくなります。
・モル計算の徹底練習:化学量論計算(モル計算)は頻出分野です。様々なパターンの問題を解き、確実に得点できるようにしましょう。
4-5-3.生物の対策
生物では、実験データを分析する力を養うことが重要です。 図やグラフを活用し、視覚的な理解を深めましょう。頻出分野である遺伝や生態系の問題に慣れるために、過去の出題傾向を分析し、類題演習を繰り返しとくと効果的です。
<対策>
・図解を用いた学習:細胞内の構造や代謝経路など複雑な内容は、自分で図解してまとめると理解が深まります。
・実験計画の考察:与えられたデータから仮説を立て、検証方法を考える練習をすることで科学的思考力が鍛えられます。
4-6.情報
情報Ⅰでは、プログラミングやデータ分析の基礎知識が問われます。アルゴリズムやネットワークセキュリティなどの基本概念を理解することが重要です。また、情報モラルや著作権などの知識も必須です。
<対策>
・プログラミングの基礎習得: 簡単なプログラムを書いてみることで、論理的思考力を養います。
・情報モラルの理解: インターネットやSNSの適切な利用方法について学び、情報社会での倫理観を身につけます。
・データ活用能力の向上: データの収集・分析・活用方法を学び、情報処理能力を高めます。
5.大学入学共通テスト本番で実力を発揮するためにできること
ここでは、大学入学共通テスト本番に実力を発揮するために、押さえておきたいポイントを解説します。

5-1.試験直前1ヶ月の過ごし方
試験直前1ヶ月は、模試や過去問を解くことで本番を想定した演習をおこない、試験形式や時間配分に慣れることを重視しましょう。苦手な分野に特に集中し、理解を深めます。また、体調管理も重要です。規則正しい生活と十分な睡眠を心掛けると、試験当日にベストな状態で臨めます。精神的にも余裕を持つため、無理のない計画を立てることがポイントです。
5-2.本番で焦らないための時間配分と解答戦略
試験本番で焦らないためには、時間配分を事前に決めておくことが大切です。各科目ごとにかける時間をしっかり計画し、効率的に解答できるよう準備しましょう。問題を解く順番は、得意な分野から取り組むと自信が持て、難しい問題にも落ち着いて挑めるのでおすすめです。すべての問題に同じ時間をかけるのではなく、配点や難易度に応じて時間を調整しましょう。マークミスを防ぐためには、大問が終わるごとに解答欄を確認する習慣をつけておくと安心です。最後に10分程度の解答の見直しをする時間を確保し、ケアレスミスを減らすためにも見直しの習慣を徹底しましょう。
6.大学入学共通テスト対策なら個別指導塾がおすすめ
効率的に大学入学共通テスト対策をするなら、個別指導塾がおすすめです。ここでは、その理由を具体的に解説します。

6-1.自分に合った学習プランを作成できる
個別指導塾では、一人ひとりの弱点や目標に応じたオーダーメイドのカリキュラムを作成できます。自分のペースで学べるため、無理なく効率的に学習を進められ、得意科目をさらに伸ばすのはもちろん、苦手科目の克服にもしっかり対応できます。特に共通テスト対策では、各科目の得意・不得意に応じた時間配分や、個人の学習スタイルに合わせた教材選びが重要です。個別指導塾なら、これらを柔軟に調整でき、限られた時間で最大の効果を得られます。
6-2.分からないところをすぐに質問できる
個別指導塾の最大の特徴は、マンツーマン指導によるリアルタイムのフィードバックを得られることです。集団指導塾や学校では、質問する時間や機会が限られることがありますが、個別指導塾なら分からない箇所をその場で解決できます。そのため、疑問を持ち越すことなく学習を進められるのがメリットです。共通テストのような思考力を問う問題は、解答プロセスの理解が重要ですが、独学では「なぜそう考えるのか」という点が分かりづらいことがあります。個別指導塾なら、問題の解き方だけでなく、その背景にある考え方まで丁寧に教えてもらえるため理解度が深まりやすく、学習効率が高まります。
6-3.共通テストの傾向に合わせた対策ができる
個別指導塾では、共通テストの最新の出題傾向を踏まえた指導が受けられます。試験で求められる思考力や判断力を重視した問題へのアプローチは、一人ひとりの理解度を踏まえる必要があるため、集合指導塾で身に付けるのは困難です。その点、個別指導塾は、生徒の状況に応じた対応が可能です。共通テストの過去問や模擬問題を解きながら、個々の弱点克服に向けて取り組めるのは、個別指導塾だからこそのメリットといえるでしょう。
7.まとめ
共通テストで成功するには、早めの対策と効率的な学習が不可欠です。試験本番までに基礎固めを徹底し、過去問演習を重ねることで、試験形式に慣れていきましょう。個別指導塾を活用すれば、自分に合った指導を受けられ、効率よく学力を向上できます。苦手克服もスムーズに進み、自信を持って試験に臨めるようになるでしょう。
個別指導塾スクールIEでは、生徒一人ひとりの学習状況やライフスタイルに合わせた柔軟な指導をおこなっています。「共通テストで高得点を目指したい」「苦手科目の克服を徹底したい」「試験直前の効率的な学習方法を身につけたい」など、共通テスト対策に最適なプランもご提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

学年別の個別指導コース
執筆者:スクールIE コラム編集部
お子さまの個性に合わせた
学習方法見つけませんか?
教育のプロフェッショナルが
保護者様の様々なお悩みに答えます!
体験授業で3つの無料体験

学校推薦型選抜とは?仕組みや一般選抜・総合型選抜との違いを徹底解説!






 受付 10:00~21:00(日祝を除く)
受付 10:00~21:00(日祝を除く)